今回は、まったくビジネスっぽくない話。いつもそうか? (笑)
もし、ビジネスっぽい話を望まれる方は、読まないことをお勧めします(笑)
昨日まで、日経新聞の「私の履歴書」を早川書房の社長 早川浩さん(会長職へ?)が書いている。私は。特に大学時代は海外ミステリにはまっていた時期があった。だからハヤカワ文庫にはお世話になった。そこで思い出し、こんなタイトルで書くことに。(「こんな」と言っても、まったくなんのこと?と思われる方が多いと思うが、お許しを)
そう、今回のタイトルは、経営学者や経営者の名前ではなく、ミステリ作家の名前。
「私の履歴書」の中で外国の作家を日本に呼ぶ企画「ハヤカワ国際フォーラム」というものを行い、その第1回で読んだのがディック・フランシスだったという記載があった。ディック・フランシスが最初に呼んだ作家だったのか、、、ディック・フランシスの本も相当読んだ。
私が海外ミステリにハマったきっかけは、元々好きだった柴田錬三郎がエッセイの中で度々、海外の小説の面白さを語っており、それから読むようになった。
最初は、フレデリック・フォーサイスやケン・フォレットのスパイスリラー的なやつ。ドゴールは暗殺されていないと知っていても、「ジャッカルの日」を読みながらワクワク・ドキドキしながら、のめりこんだ。ジョン・ル・カレ、トレヴェニアンなんかも読んだが、次第にハードボイルド系統にもはまっていった。早川社長の私の履歴書に、何度か登場したロバート・B・パーカーも読んだが、やはり、ハメット、チャンドラー、マクドナルドが好きだった。個人的には、チャンドラーのフィリップマーロウも好きだが、ロス・マクドナルドのリュウ・アーチャーの乾いた質問者という感じが好みだった。もちろん、これら3人の大御所以降のネオハードボイルド的なものも読んだ。
でも、作家として、作品として最も好きだったのは、ジャンルは冒険小説になるのか?今回のタイトルにした「ディック・フランシス」「ギャビン・ライアル」だった。
当時は、ディック・フランシスの本は、ハヤカワミステリ文庫の中で探しやすかった。タイトルがすべて漢字2文字だったから。「興奮」「大穴」「重賞」「本命」・・・と目立った。そして、このタイトルから想像がつくと思うが、競馬シリーズだ。私は競馬は当時も今もしない、最初は、競馬の本なんておもしろいのかな?と思いながら一冊読んだら、競馬を知らなくても面白く、次々と読んでいくようになった。当時出ている本はすべて読みつくし、その後の新作が出るのが楽しみだった。だから一部文庫化が待ちきれずに買った本もある。
好きな本は沢山あるが(「血統」も好き)、やはり代表作である、元騎手の探偵で落馬事故で片手が不自由な シッド・ハレーのシリーズは面白い。基本、ディック・フランシス作品は一話完結だが、このシッド・ハレーは「大穴」「利腕」「敵手」「再起」と登場する。あまり内容は書かないが、「利腕」にこんなことが書いてある。拷問され、脅迫されるシーン。「人がなんといおうと、恐怖というものを私は充分に承知している。それは馬そのもの、レース、落馬、あるいはふつうの肉体的苦痛に対する恐怖ではない。そうではなくて、屈辱、疎外、無力感、失敗・・・それらすべてに対する恐怖である」そういった状況を通り抜け「自分が永遠に対応できない、耐えられないこと、それは自己憐憫である」というセリフが出てくる。何にも負けないスーパーマンではない、傷つき、痛みを感じる。だけど立ち上がる姿に感じるものがあった。
そして、ギャビン・ライアル。ディック・フランシスは、元々騎手だった。一方ギャビン・ライアルは、元空軍パイロットだ。彼の小説は、特に初期は飛行機に関係するものが多い、中~後半は、陸軍ものからスパイものになっていく。こちらも面白い本は沢山あるが、やはり秀逸なのは、「深夜プラス1」「最も危険なゲーム」の2冊だ(まったく同じ本を3冊づつ持っていた)。内容は書かないが、「深夜プラス1」のラストのシーンは、素晴らしい。あるひどいことをした主人公。「手軽で簡単に、少しむごいがね」「カントンはこうしたに違いない。おれが別の人間だったら、もっといい方法を思いついたかもしれん。しかし、これがおれのやり方なんだ」、、、友情、自分のルール・自分の中の正義、プロフェッショナル、様々な要素が詰まっている。世の中の価値観からすると、いいかどうかはわからない、しかし本人にはルールがある。ここまではやるがここからはやらない。ここまでは譲っても、これ以上は譲れない。流されないものを持っている。
今回は、まったく?ビジネスっぽくない内容で、あまり関心のない方には、ここまで読んでいただき、申し訳ない面もあります。
ただ、屁理屈っぱいかもしれないけど、経営・マネジメントの根底にあるのは、その人の人生観そのものであり、私の人生観の一端は、これらの本によってもたらされている、、、かもしれない。



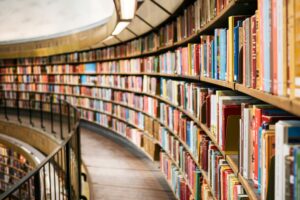





コメント