私は、歴史が結構好きだ。日本の歴史も好きだが、海外の歴史にも興味がある。今回は、その中でも中国の歴史の話し(個人的趣味)。
最も好きな人物は、諸葛孔明(三国志 蜀の国の丞相)だが、今回は、その孔明が若い頃、自らをなぞらえていたという話もある管仲の話し。
管仲は、中国の春秋時代(紀元前770~453年)、群雄が割拠していた中で、最初の覇者となった斉という国の桓公に仕えた宰相だ。(歴史的には、春秋時代ってどんな時代?とか、覇者って何?とか、桓公って誰?とか、解説が必要だが、ここでは割愛します)
大昔のことなので、どこまでが事実かはわからないが、桓公が覇者になったのは、管仲の力によるところが大きいというのは、ほぼ見解の一致するところだと思う。管仲に関する数あるエピソードと、それらをつなげて考えると、管仲の思想観が伺える。
- 民を富ませる・・・富国強兵でいうと、まずは富国!という考え方があったと思う。外に対して戦う前提として、国と民を富ませることが最優先という考え方とそれに基づく取り組みが見える。「倉廩満ちて礼節を知り、衣食足りて栄辱を知る。」という言葉も管仲によるものとされている。斉の国では(各種施策は省くが)、管仲は物価安定や産業の活性化に取り組み、民は豊かになり、人がこぞって斉の国に集まったという。そして、そこから優秀な人材を登用していった。
- 信頼の上に様々なことが築き上げられる。という考えもしていたと思う。これもいくつかエピソードはあるが、例えば、斉が隣国である魯を攻め、領土を奪った時の話しがある。その調印の際、魯の将軍曹沬は、桓公の首に匕首を突きつけて奪った領土を返還する事を要求した。やむなく桓公はそれに応じたが、斉へ帰った後に「脅迫された盟約など守る必要はない。領土を渡す必要もないし、今一度魯を攻め、曹沬を殺す」と言った。しかし管仲は「たとえ脅迫の結果であっても、一度した約束を破って諸侯の信望を失ってはいけません」と諌め、領地を返させた。こういったことが、他の国々にも広まり、斉の桓公は、決して約束を違わない人物という評判がたち、他の国々から信頼され、相談され、というようになったという。
- 他者(他国や自国の民等)が、どう感じ、考えているかを踏まえた行動も意識していたと思う。桓公が狩りに行ったときに愚公と呼ばれる老人に会った。愚かに見えないその老人になぜ愚公なのか?と聞いた。その老人は、こう答えた。以前牛を飼っていたが、その子牛が大きくなったのでそれを売って仔馬を買ったところ、一人の若者が、牛が馬を生むはずがない、といい、仔馬を連れ去ってしまった。近所の者はそれを聞いて愚かだと笑った。桓公は確かに愚かだと思った。翌日その話を管仲にすると、管仲は襟を正してこう言った。「それは私の過失です。もしきちんと世が治まっていれば、人の仔馬を奪うものは現れないはず。老人は自分のものを決して渡さなかったでしょう。その老人は法や罰が正しく行われていないので、訴訟しても無駄だと知って、仔馬を奪われようとしたときに争わず、奪われた後も役人に訴えなかったのです。どうか、退出させていただき、政治を修正したいと思います。」
宮城谷昌光は、その管仲を評して、「管仲が行ったのは、貴族のためではなく庶民のための政治である。しかも、この耳の良さはどうであろうか。政治を行うものは無言の声を聴き取る耳の良さを持っていなければ善政を行うことはできない」と言っている。
管仲のエピソードは、有名な管鮑の交わりなど他にもたくさんある。また、一方で管仲のことを批判する人もいる。事実は、わからないし、ここでは人物評をしようというわけではない。ただ、管仲の各種施策は(ここで触れないが)、この時代にそんなことをよく、、、と感じるものも多い。管仲は結構ロジカルで合理的な側面ももっていたようなので、上記のような価値観の下、色々考えたのだと思う。その結果、この時代に安定をもたらした。
管仲の話しは、紀元前の群雄割拠していた春秋時代の話し。ただ、今でもとっても大事なことが含まれているように思える。我々が学べることがあるのでは、と思うだけである。社員を大切にする経営、CS(Customer Satisfaction:顧客満足)の前にES(Employee Satisfaction:従業員満足)、心理的安全性、その他 組織運営やリーダーの在り方 等々



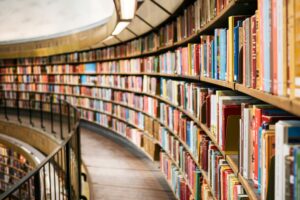





コメント