管理者研修等で管理者の方々と接していると、「やりにくくなった」という話を時々耳にする。近年、「パワハラ」等のハラスメントに関する法律その他の対応が厳しくなり、部下指導・育成がやりにくくなったということのようだ。確かに、私が若い頃?は、今だったらそれはパワハラでアウト!一発退場!というような事象は、日常頻繁にあったようにも思える。でも一方で、厳しい上司だったけど、「パワハラ」というより、「指導」と思える上司も存在した。
武経七書と言われる7つの兵法書がかつての中国にある。もちろん有名なのは「孫子」。その中で最も新しいものが「李衛公問対」(りえいこうもんたい)になる。
李衛公問対は、唐の太宗:李世民(「貞観の治」「貞観政要」などが有名?)とその臣である李靖の対話形式になっている。李靖は、唐建国にあたって、乱立した他の国々や北方民族等を相次いで倒し、参謀、将軍的な役割、そして宰相まで務めた人物で、若い頃から兵法に詳しかったらしい。個別の戦いについては省略するが、緻密な計算に基づく、勇猛果敢な戦いで負け知らずだった。李衛公問対では、太宗李世民が質問し、李靖が回答するという形式になっている。「孫子」に関する記述もあり、その後の様々な武将が事例に取り上げられたりしていて、読みやすい。(興味ある人はどうぞ)
その中にこんなくだりがある。(そうとう意訳しながら)
太宗が、よく必要と言われる厳しい厳罰や刑法は本当に有効なのだろうか?と例を挙げて李靖に問いかけると、李靖は様々な状況があるので、一つの事例だけで決めつけることはできないが、軍の厳しさが勝利を呼ぶわけではないと話したうえで、「孫子には『兵士がまだ懐いていないのに兵士を罰すれば心腹しない。しかし、既に懐いているのに罰を行わなければ用いることはできない』とあります。これは、そもそも将たる者は、先に兵士を可愛がり信頼関係ができて、その後になって初めて厳しい刑罰を用いるべきことを言ったものです。もし、兵士を可愛がってもいないのに、軍法を果断に用いるのならば、ことを全うすることは非常に難しいでしょう」と言っている。
また、李靖は「愛することが先にあり、威は後回しにする。これに反してはなりません。もし、威を先に加えて、愛でこれを取り繕うということなれば、何も利益はないでしょう。」「孫子の(先に述べたこと)法は万代変わらぬ法なのです」
また、李靖が反乱軍を鎮圧した時のことを用いて、太宗は「諸将軍は、皆裏切った家臣の財産を没収して、兵士たちに報酬として分けることを主張したが、李靖だけは反対した」という話をした。李靖は後漢の光武帝の例を挙げ「漢の光武帝が農民の反乱軍(赤眉軍)を平定したとき、賊から『王の真心は腹にまでしみいるかのようですな』と言われた。彼らも本質は悪でなく、生活苦によって仕方なく悪行をしてしまったということを推し量っていた上でのこと。このように人を懐かせる心とは、真心なのであり、普段からの思いやりがなければ、誰も懐いてくれないのです。計算では成し得ない」と語っている。
思い返すと、厳しいけれど信頼できる上司は、その根っ子に部下への愛情があったように思う。だから、その人の言うことに従う。また、更に進んで、その人についていこうと思う。
逆に、部下がそう思えない上司は、やはり(悪意はないにせよ)視線が、関心が、自分に向いていて、部下に向いていないのだと思う。無意識に、部下のためにではなく、自分のためにが優先されるのだろう。低い自己肯定感や自己効力感によって、部下が自分の思い通りにならない状況というのを受け入れられない。その状況を変えようとして、罰を与える。罰と思えるような言葉を浴びせかける。
李靖のような、命を賭して様々な任務にあたった ある種の軍事家が言っていることは重く感じる。様々な状況においても、組織としてことをなすためには、権威やポジションではなく、人間力が必要なのだと思う。もちろん、法や威はいるのだと思うが、順番が大事なのだろう。
パワハラ関係の法律が整ったからとかは関係なく、李靖が言うように「愛することが先にあり、威は後回しにする。孫子の法は万代変わらぬ法なのです」・・・これは古の時代から普遍的なものなんだと思う。
参考:「兵法武経七書 李衛公問対」訳文・解説 平田 圭吾



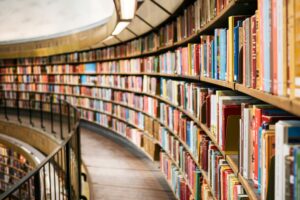





コメント