前にも書いたが、私は、大学を卒業し、コンサルタント会社(教育会社)に入社した。その会社のキャリアパスは、営業を経験してからコンサルタントになるというものだった。私の配属は高松営業所。四国四県を担当していた。そして当時、新入社員は新規開拓を専門に行っていた。
ある日、私は当時の営業所長からこう言われた。「お前、宇野に行ってみるか?」
宇野とは、高松とは瀬戸内海を挟んだ対岸、つまり岡山県の中小都市だった。(現玉野市)
私は、フェリーで高松から宇野に渡り(瀬戸大橋はまだ)、貸し自転車屋を探し、町の中を走って回った。宇野は、当時三井造船の城下町といった様相を呈していた。
3日位行って営業をしたが、いい話にはならなかった。当時の私のセールス力のなさもあったと思うが、ほとんどのお客様から似たようなことを言われた。
「うちは、三井造船の下請け的な仕事をしている。でも今は、造船不況。最近は、三井造船も冷たくなった。長年の付き合いだといっても、どこか遠くの会社が我々より少し安い金額で仕事を請け負うと言ってくると、そちらに仕事を出してしまう。ただ、そうは言っても、昔は三井造船にいい思いをさせてもらったのも確かだ。」
「このままではやっていけない。造船が悪いから新しいことをやってみようと思っても、まずお金がない、新しいことをやる人がいない。そして、今までずっと三井造船の下請けをしていたので、新しいことをやるノウハウがない。海の近くだから、釣りをする人向けのうどん屋でもやろうかという話も出てる。でもそれもうまくいくとは限らないし・・・昔、造船がいいころに何かやっておけばよかったんだけど・・・」
当時私は、新入社員なりに思った。いい時にどうするかが大事なんだ。いい時にどう過ごすかが、永く続くかどうかに大きく影響するのだと。悪い時は、みんな課題や問題が分かっている。そして、取り組まなければ大変なことになる!という機運が組織内にある。でも、いい時は、問題点があまりクローズアップされない。将来のリスクには、目が向きにくく、今をどう回すかに目が行きがちになる。将来を考えても、切実感が薄くなる。
それらをしっかり組織全体で認識するためには、①目指すところをしっかり確認する必要がある。使命感だったり、将来ビジョンだったり。・・・それと照らして、本当にこれで十分か ②先を見通す力もあったほうがいい。・・・今は良くても、環境変化の中に様々なリスクが潜んでいる 等が必要だと思う。
また、それらができるためには、次の様なことも重要になってくると思う。①経営陣の物の見方の柔軟性(思い込みを持たずにセンサーで感受すること) ②様々なネットワークがあり、フィードバックやアイデアなどの各種情報が集まる。情報が考えるきっかけになるので、社内外を問わず、関係を育み、他者の見解を受容することができること(鵜呑みにするのではなく)。・・・支え、助けてくれる人がどれだけいるかも重要。
もちろん、多くの変革・チェンジに関する学者が言っていることではあるが、あの時の実体験があるため、私は、難しいかもしれないけど、いい時に将来に向けた手を打っておかないと、後で大変なことになるという感覚がある。



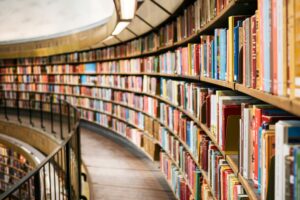





コメント