この仕事をしていると、「自分で考える」ということの重要性は、よく痛感する。わかりやすいところでは、業界が同じだからといって、A社が~~に取り組んで成功しているから、業界が同じB社も~~に取り組めば成功するとは限らない。同じ業界にいるといっても、様々なことが複雑に絡み合っているため、まったくの「合同」はない。だから、同じようなことをする=同じ結果になる ということはない。
これは何も戦略的な領域だけではない。営業の世界でもそうだし、職場での問題解決、人間関係もそうだ。唯一絶対の正解が見出しにくい社会科学の領域では、一つの回答のパターンをマスターしたとしても、それがいつも使えるわけではない。だから、自分で考え、答えを導き出すことが大事になる。
そういった意味では、「ゼロ秒思考」(赤羽雄二)に書かれていることは、理にかなっているように思う。(本の内容は省略しますが、興味のある方はぜひ読まれては?)人は切羽詰まっていると、当然真剣に考える、そして結論を出さねばならないので、考えた結果を曖昧にしないでクリアにする必要がある。そういった状況を模擬的に作り出し、思考を鍛えていく。
だいぶ前に読んだ本で「人生、惚れてこそ(知的競争力の秘密)」という将棋の米長邦雄と羽生善治の対談本の中の勉強法に関しての話のところで「昔、ある農村に算数のすごくできる子どもがいた。しかし、家が貧しいので中学校に行けなかった。彼は百姓をしながら、一生懸命、独学で算数の勉強をした。それで10年経ったとき、大発見をしたと言って、小学校の先生のところに来た。その発見とは二次方程式の解き方であった。この少年が中学校へ行っていたら、一年生の最初に習うことであった。独学の彼はそれを知るのに10年かかった。その能力をもっと違うところに使っていたら・・・。ああもったいない」という宮崎市定さんの話を引用している部分があった。
今、経営コンサルタントや研修講師の仕事をしていて思うのは、学べていない社員が意外と多いということ。特に気になるのは、中途採用社員のケースと異動による配置転換のケースだ。新しい仕事につくが、そこで仕事を学び、身につけることが非常に非効率な感じがする。具体的にいうと、当面のやる仕事はわかっても体系立てて教えられていない、どこに情報があるかわからない、等の状況の中で、仕事がうまくいかなかったり、ミスしたり、結果怒られたりする。そして、モチベーションが下がり、自信をなくし、、、という状態。
本人の問題と上司や組織の問題と両方あると思う。組織内が、学習することを奨励し、学ぶ人が認められ、人のために教える人が尊重されるような風土を作っていくことが必要だと思う。
「学ぶ」の語源は「まねぶ」(真似する)だと聞いたことがある。先ほどの「人生惚れてこそ」の中で、羽生善治はこんなことも言っている。(私の意訳した解釈)「将棋って難しすぎる、だから先人の通った道を見よう見まねで覚える。そして、時間がたって、真似から、ああそうかという理解になっていく」
「真似する」と「自分で考える」は両方大事だと思う。若い頃や何かを始めたばかりの頃とベテランになってから、時期やタイミングなどによって、「真似する」と「自分で考える」のどちらにウェイトを置くかは変わるかもしれない。また、「真似する」を通して、本当にそれでいいのか?違った方法はないか?と「自分で考える」ことも必要だし、「自分で考える」その結果、それで本当にいいのか?と先人の方法と照らし合わせることも大事だと思う。
書きながら、自分を振り返り、う~~ん 自分もこの2つ、更にレベルアップしなければ!と思う



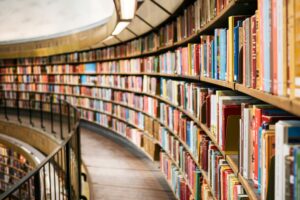





コメント