この前、「『ついていきたい』と思われるリーダーになる51の考え方」岩田松雄(元スターバックスコーヒージャパンCEO)の本を読んだ。読みやすくて、面白かったがその中にこんな話があった。(全体的にこういったトーンのメッセージが多いように感じた)
(だいぶ意訳しているかも、、、すいません)
部下は上司のことをよく見ている。ついていきたいと思われるリーダーは、苦しんでいる人の気持ちがわかる。人の痛みのわかるリーダーが待ち望まれている。組織では部下にいかに動いてもらうかが大事、だから目を向けるべきは、現場であり、そこで働いている人たち。リーダーは、強い立場にいるからこそ、組織の中で弱い人に目を向ける必要がある。
そんなことが書かれていた。世の中には、様々なリーダーがいる。残念ながら、部下からすると、ついていきたいと思わないリーダーも多い。(そのことだけで責めるつもりはないが)
下記のような話を思い出した。
石田三成と大谷吉嗣
豊臣秀吉が主催した茶会で、一口ずつ茶を回し飲みする場面があった。大谷吉嗣は病(らい病という説も)があり、彼の番で茶碗が回ってきたとき、彼の顔から膿が茶碗に落ちてしまいまった。これを見た周囲の人たちは、茶を飲むのをためらったが、石田三成は迷うことなくその茶を飲み干した。
大谷吉嗣は、自分の信念に従ってというところも大きかったと思うが、関ヶ原の戦いにおいて、石田三成の西軍に加わり、病身を押して戦い、壮絶な最期を遂げた。
楚の荘王
中国の春秋時代、楚の国の荘王は臣下たちを宴に招いた。皆が酒を飲み、楽しんでいると、突然、灯りが消えてしまった。その暗闇の中で、ある者が王の愛妾に無礼を働いた。愛妾は咄嗟にその男の冠の紐を引きちぎり、誰が無礼を働いたかを後で特定できるようにした。しかし、荘王は「今夜は無礼講だ」と言い、明かりをつける前に全員に冠の紐を切るよう命じ、その者が特定されないようにした。
数年後、楚が秦との戦争を行ったとき、常に先頭に立って勇敢に戦う家臣がいた。荘王は、満身創痍になりながらも大功を立てたその家臣を呼び、「なぜあれほどの働きをしてくれたのか」と尋ねた。家臣は、「以前、酒に酔って王の愛妾に無礼を働きましたが、王のお情けによって命を永らえることができました。その恩に報いたいと願い続けておりました」と答えた。そして、その家臣はその場で命を落とした。
現代企業の中だけでなく、歴史の中のこういった事例もたくさんある。
困っているときに、手を差し伸べてくれた恩を人は忘れない。その人のために、と思える。しかし、計算してそういった行為をしていると、部下はよく見ていて、どこかでほころびを生じる。
部下のことを想っているいるからこそ、部下からも想われる。上記のような事例は、すべての部下に対してということはない。でも、そういうことをする人だということを他の部下はよく見ている。
自分のことばかり考えると、どうしても力の強い人のことが気になる。弱い立場の人のことはおざなりになる。分け隔てなく、弱い人にも目を向け、思いやることが、周囲の人から「この人のために!」と思われるリーダーにつながる。リーダーは、フォロワーがいて、初めてリーダーと言える。
テクニックではなく、どうすれば、そういった自分になれるか?ということが、ここで浮かび上がってくる。が、長くなるので、この辺の話しは、また別のときに。



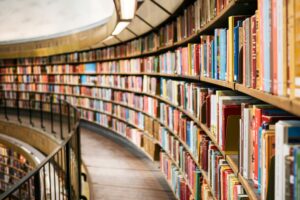





コメント