正月は、年賀状のやりとりをする。そうすると、懐かしい人たちからの便りが届く。最近あまり会わない大学時代の仲間からの年賀状も来ている。
私は、大学時代、経営戦略をテーマにしたT先生のゼミに入っていた。T先生は既に退官されている。今も年賀状のやり取りはさせていただいている。
何年か前の先生の退官前後、色々なイベントがあった。何人くらいが集まったのだろう。かなり多くのOBが集まっていた。不覚にもジーンとし、涙してしまった。書きたいことはたくさんあるが、なぜこのゼミは、こんなに卒業生が集まってくるのだろうか。そんなことを自分なりに考えてみた。(我々の同期も数年前に集まった時、東京にいないメンバーもいるが、16名中15名が集まった)T先生は、必ずしも「俺について来い!」的な先生であったり、生徒と深い個人的関係を結ぶタイプの先生ではない。(先生ごめんなさい!)でも、これだけの人が集まり、笑い、涙し、また会いたいと思う。
ゼミの特徴は、
・ 勉強を結構した(ある意味、せざるを得なかった)。ゼミが始まるのは、3年生からだったのに、2年生の秋以降から、勉強会と称する予習があった。・・・これは先輩たちに指導されるもので、先輩が結構厳しかった。他のゼミに比べても勉強したと思う。(他のゼミの方・・ゴメンナサイ)
・ 共同論文・・・3年生のゼミ活動は、この共同論文だった。期によって違うが、同期で1~2業界を選択し、その業界に登場する企業を複数研究し、皆で議論しあって、論文をまとめるものだった。
・ よく遊んだ・・・飲み会はもちろん。合宿旅行。映画鑑賞。テニス、その他そうとう遊んだ。
なぜ、このゼミはこんなに結束力が強いのか?(同級生同士で仲がいいというのは、よくあることだと思うが、世代を超えてまでというのは、少ないのでは・・・)私の中でも結論ははっきりと出ていないが、私がキーワードとして考えているのは、下記のようなことだ。
・ 【共通体験を通じての仲間意識】特に苦労しながらも、助け合い、共同論文を作り上げたという達成感が、仲間意識に繋がる。また、世代を超えても、同じような体験をした仲間という意識がある。
・ 【本音が言い合える関係】共同論文の作成を通して、本音で(時にはケンカのように)やりあった経験は、お互いが腹蔵なく言い合える関係をつくる。
・ 【個人:人間としての繋がり】知識や学問領域による繋がりよりも、個人個人(人間として)の繋がりの方が深い。大事なのは人間そのもの。人間性であったり、人生観の形成であったり。
・ 【他者支援・尊重の雰囲気】仲間を助けようという指向性がある。これは、ゼミ創設の頃、先生から初期のゼミ生の先輩へ。そして、その後、先輩から後輩へと自分が受けた愛情(?)を下に受け渡すように脈々と流れるような気がする。
・ 【愛情を注がれているというと感覚】T先生は、我々に対して、子供のように愛情を注いでくれている。いつも気にかけてくれている。単に教授と学生という関係以上のものを我々は感じている。
こういったことは、単に大学のゼミの範囲内に留まらず、社会に出て働く中で、知らず知らずのうちに我々卒業生が、大事だと感じることであり、そういった体験をさせてくれた「ゼミ」に、無意識に感謝しているのだと思う。私も「ゼミ」「T先生」「先輩・後輩」「同期の仲間」に感謝している。
ビジネスの世界でも、そういった関係が築ければと思う。お金のやりとりだけでなく、相互にいい影響を与えられる関係。



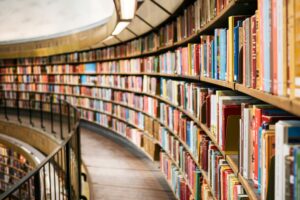





コメント